×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
職場の一先輩として若手とどう向き合うべきか、という目の前の課題が一段落したところで…。
「本来業務」の課題ですorz
『プロジェクト・マネジメント実践講座』(B&Tブックス) 芝 安曇・小西 喜明
AMAZONの商品ページはこちら。
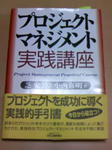
10年以上前(1999年発行)の単行本です。
大人数で、それなりに確立されたウォーターフォールで開発していく職場から、
個人のカンと経験と曖昧力と…で仕事しなければならない今の職場に移り、
ふつふつと湧き上がった疑問が、
「もう少し、シロウトにも出来るような仕事のフレームワークを作れんのか?」
そこで、一通りの知識があるPMBOKという「仕事の型」に落とし込むため、
参考になりそうな具体的な実践例を求めて、
買いあさった書籍群の1冊だったと記憶しています。
著者がシステムの人ではなくプラントの人たちなので、
システム目線のみでPMBOKを勉強してきた自分にとっては、
また少し異なる視点を学べた気がします。
理解の抽象度が、一段上がった感覚です。(曖昧で申し訳ない)
ウォーターフォール型のシステム開発に特化した自分のPMBOK理解を、
本来の、もっと広い意味での「プロジェクト」の目線に戻して、
そこから今の仕事に適用していけないかなぁ…と、模索しているところです。
…
と、特殊な読み方をした自分の感想はともかく、
もう少し本書の中身に沿った感想も書いておきます。
・ 世の中のプロジェクトを「構想計画」「実施計画」の2フェーズに分け、
特に前者に力を入れて解説しています。
「構想計画」=システム開発で言うと超上流工程か???
・ 「実施計画」を解説している章では、セミナーや家族会議など、
対話を想定しながらの具体例が豊富。
若干初心者向けかのぅ?とか思っていると、
「WBS」の本来の姿がさりげなく掲載されていて(OBS×FWBS)、
「システム開発用にカスタマイズされたPMBOK」しか知らない自分を
改めて発見できたりします。
(※「システムのWBSはプロセス主体だが、
本来成果物主体だったのではなかったか」という疑問が、
最近自分の中で沸き起こっていた関係で目に付いた)
・ ちなみに、世の中のプロジェクトは、いくつかにタイプ分けされるとか。
「目的不明確型」 : 思いつきプロジェクト。さっさと終わらすべし
「目的不透明型」 : システム開発など
「目的明確型」 : プラント建設など
「目的探索型」「目的追求型」 : 研究開発
今の職場でよく巻き込まれるのが、「目的追求型」の案件。
…これだけ違うもののプロセスを同じ言葉で語ろうとするのがPMBOKなんだから、
そりゃあ現場で実践の段階になったら、相当なカスタマイズが必要だよね、と思うわけです。
おっと、結局、自分固有のの課題感に沿った感想文になっちゃった(^^;)
「本来業務」の課題ですorz
『プロジェクト・マネジメント実践講座』(B&Tブックス) 芝 安曇・小西 喜明
AMAZONの商品ページはこちら。
10年以上前(1999年発行)の単行本です。
大人数で、それなりに確立されたウォーターフォールで開発していく職場から、
個人のカンと経験と曖昧力と…で仕事しなければならない今の職場に移り、
ふつふつと湧き上がった疑問が、
「もう少し、シロウトにも出来るような仕事のフレームワークを作れんのか?」
そこで、一通りの知識があるPMBOKという「仕事の型」に落とし込むため、
参考になりそうな具体的な実践例を求めて、
買いあさった書籍群の1冊だったと記憶しています。
著者がシステムの人ではなくプラントの人たちなので、
システム目線のみでPMBOKを勉強してきた自分にとっては、
また少し異なる視点を学べた気がします。
理解の抽象度が、一段上がった感覚です。(曖昧で申し訳ない)
ウォーターフォール型のシステム開発に特化した自分のPMBOK理解を、
本来の、もっと広い意味での「プロジェクト」の目線に戻して、
そこから今の仕事に適用していけないかなぁ…と、模索しているところです。
…
と、特殊な読み方をした自分の感想はともかく、
もう少し本書の中身に沿った感想も書いておきます。
・ 世の中のプロジェクトを「構想計画」「実施計画」の2フェーズに分け、
特に前者に力を入れて解説しています。
「構想計画」=システム開発で言うと超上流工程か???
・ 「実施計画」を解説している章では、セミナーや家族会議など、
対話を想定しながらの具体例が豊富。
若干初心者向けかのぅ?とか思っていると、
「WBS」の本来の姿がさりげなく掲載されていて(OBS×FWBS)、
「システム開発用にカスタマイズされたPMBOK」しか知らない自分を
改めて発見できたりします。
(※「システムのWBSはプロセス主体だが、
本来成果物主体だったのではなかったか」という疑問が、
最近自分の中で沸き起こっていた関係で目に付いた)
・ ちなみに、世の中のプロジェクトは、いくつかにタイプ分けされるとか。
「目的不明確型」 : 思いつきプロジェクト。さっさと終わらすべし
「目的不透明型」 : システム開発など
「目的明確型」 : プラント建設など
「目的探索型」「目的追求型」 : 研究開発
今の職場でよく巻き込まれるのが、「目的追求型」の案件。
…これだけ違うもののプロセスを同じ言葉で語ろうとするのがPMBOKなんだから、
そりゃあ現場で実践の段階になったら、相当なカスタマイズが必要だよね、と思うわけです。
おっと、結局、自分固有のの課題感に沿った感想文になっちゃった(^^;)
PR
このところ若手育成だの新人現場リーダーの心得だの、そんな本ばかり読んでいましたが、
それもひと段落したので、久々にシステム関連本をレビューして見ます。
・ 『ソフトウェアエンジニアリング講座1 ソフトウェア工学の基礎』 ITトップガン育成プロジェクト(日経BP)
AMAZONの商品ページはこちら。

2010年2月読了。
…この本を手にしたきっかけは、
職場の若者が社内の研修で「ソフトウェアエンジニアリング研修」とやらを受けることになったこと。
後輩に研修の感想を聞いて、質問して、フィードバックするに当たって、
話を振る私のほうに、基礎知識がないのはまずいよね、と思って、こそっと購入しました。
まー実際観てみたら、システム屋を何年かやっている人間ならどこかで聞いたことばかり書いてあったんですが、
「ああ、こーゆー知識体系のことを、世間ではを『ソフトウェアエンジニアリング(ソフトウェア工学)』っていうのね!」と合点が行きました。
くそぅ、脅かしやがって!(><。)(笑)
その、システム工学の知識体系のうち、
本書で解説しているのはこんな感じの項目たち:
■ SWEBOKに基づく知識領域(の一部)
・ ソフトウェア要求
・ ソフトウェア分析/設計
・ ソフトウェア構築(詳細設計、コーディング、品質・構成管理 etc)
・ ソフトウェアテスト
それに加え、関連知識としてこんな内容も:
■ ソフトウェアの歴史
・ プログラミング言語の発達
・ システムアーキテクチャの変遷
・ ネットワークの進化
■ ソフトウェアに関する法律
・ 著作権
・ 特許権
・ 開発の契約
プログラミング言語の歴史の部分なんかは、以前紹介した
『Javaでなぜつくるのか』を連想するけど、
こちらのほうがハードウェアの話も突っ込んで書いているので、
さらに広くこの世界の歴史をたどる上では、より参考になるかも。
ま、なにせ「基礎」なので、これを取っ掛かりに、
必要に応じて各分野を深掘りしていく…というのが正しい読み方でしょう。
すでに実務経験があり、広く浅く他の分野のことも知りたい人にもオススメしたいです。
(ホントの新人や学生さんには、確かにタイクツなだけかも…)
ちなみに、この本、
北大大学院で開講された「ITトップガン育成講座」(すげー名前^^;)の
内容をまとめたシリーズの1冊目(全4冊)だそうな。
執筆者、すなわち上の講座で講義した人たちの一覧には、
ギョーカイの有名どころの企業(日本I○M、マイク○ソフト、富○通ほか)の
偉い人っぽい方たちの名前が並んでおります(><)
私が学生だったら、こんな講義、怖くて受けられねえッ!(><)(笑)
…
なお、冒頭で述べた社内研修を受けてきた若手とは、研修の感想をヒアリングしている最中に、
なぜか「プログラムの著作権」というテーマで異様に盛り上がりました。
著作権法上は、ある言語のプログラムを別の言語に「翻訳」することを、
リアルの自然言語の「翻訳」と同じ扱いにしてるんだってよ。
知ってた? 知ってた?
(「COBOLをJavaに置き換える」みたいな案件、どうやってその辺をクリアしてるんだろうね~。謎。)
それもひと段落したので、久々にシステム関連本をレビューして見ます。
・ 『ソフトウェアエンジニアリング講座1 ソフトウェア工学の基礎』 ITトップガン育成プロジェクト(日経BP)
AMAZONの商品ページはこちら。
2010年2月読了。
…この本を手にしたきっかけは、
職場の若者が社内の研修で「ソフトウェアエンジニアリング研修」とやらを受けることになったこと。
後輩に研修の感想を聞いて、質問して、フィードバックするに当たって、
話を振る私のほうに、基礎知識がないのはまずいよね、と思って、こそっと購入しました。
まー実際観てみたら、システム屋を何年かやっている人間ならどこかで聞いたことばかり書いてあったんですが、
「ああ、こーゆー知識体系のことを、世間ではを『ソフトウェアエンジニアリング(ソフトウェア工学)』っていうのね!」と合点が行きました。
くそぅ、脅かしやがって!(><。)(笑)
その、システム工学の知識体系のうち、
本書で解説しているのはこんな感じの項目たち:
■ SWEBOKに基づく知識領域(の一部)
・ ソフトウェア要求
・ ソフトウェア分析/設計
・ ソフトウェア構築(詳細設計、コーディング、品質・構成管理 etc)
・ ソフトウェアテスト
それに加え、関連知識としてこんな内容も:
■ ソフトウェアの歴史
・ プログラミング言語の発達
・ システムアーキテクチャの変遷
・ ネットワークの進化
■ ソフトウェアに関する法律
・ 著作権
・ 特許権
・ 開発の契約
プログラミング言語の歴史の部分なんかは、以前紹介した
『Javaでなぜつくるのか』を連想するけど、
こちらのほうがハードウェアの話も突っ込んで書いているので、
さらに広くこの世界の歴史をたどる上では、より参考になるかも。
ま、なにせ「基礎」なので、これを取っ掛かりに、
必要に応じて各分野を深掘りしていく…というのが正しい読み方でしょう。
すでに実務経験があり、広く浅く他の分野のことも知りたい人にもオススメしたいです。
(ホントの新人や学生さんには、確かにタイクツなだけかも…)
ちなみに、この本、
北大大学院で開講された「ITトップガン育成講座」(すげー名前^^;)の
内容をまとめたシリーズの1冊目(全4冊)だそうな。
執筆者、すなわち上の講座で講義した人たちの一覧には、
ギョーカイの有名どころの企業(日本I○M、マイク○ソフト、富○通ほか)の
偉い人っぽい方たちの名前が並んでおります(><)
私が学生だったら、こんな講義、怖くて受けられねえッ!(><)(笑)
…
なお、冒頭で述べた社内研修を受けてきた若手とは、研修の感想をヒアリングしている最中に、
なぜか「プログラムの著作権」というテーマで異様に盛り上がりました。
著作権法上は、ある言語のプログラムを別の言語に「翻訳」することを、
リアルの自然言語の「翻訳」と同じ扱いにしてるんだってよ。
知ってた? 知ってた?
(「COBOLをJavaに置き換える」みたいな案件、どうやってその辺をクリアしてるんだろうね~。謎。)
『ソフトウェア開発201の鉄則』アラン・M・デービス・著、松原友夫・訳 (日経BP)
AMAZONの商品ページはこちら。

数年前に読了、レビュー掲載に当たって、2009年8月再読。
1ページあたりに1つの「鉄則」とその解説を記述する構成で、全201条。
「鉄則」というのはちと言い切りすぎで、
「ソフトウェア開発に関する201の格言」と言いかえるとちょうどいいかも。
201条が適当に並んでいるわけでなく、
ちゃんとソフトウェア開発のフェーズや管理エリアに分けて、章立てされてます、はい:
・ ソフト開発全般
・ 要求分析
・ 設計
・ コーディング
・ テスティング
・ 管理
・ 製品保証
・ 進化
どこから読み始めてもかまわないので、
自分が経験ある分野から読み始め、続けて興味のある章を読むとよいでしょう。
AMAZONの商品ページはこちら。
数年前に読了、レビュー掲載に当たって、2009年8月再読。
1ページあたりに1つの「鉄則」とその解説を記述する構成で、全201条。
「鉄則」というのはちと言い切りすぎで、
「ソフトウェア開発に関する201の格言」と言いかえるとちょうどいいかも。
201条が適当に並んでいるわけでなく、
ちゃんとソフトウェア開発のフェーズや管理エリアに分けて、章立てされてます、はい:
・ ソフト開発全般
・ 要求分析
・ 設計
・ コーディング
・ テスティング
・ 管理
・ 製品保証
・ 進化
どこから読み始めてもかまわないので、
自分が経験ある分野から読み始め、続けて興味のある章を読むとよいでしょう。
SEの現場シリーズ『SEのための仕様の基本』山村吉信・著 (翔泳社)
AMAZONの商品ページはこちら。

2009年8月読了。
最近の仕事で、
「要件定義 ⇒ 設計(仕様)」 のところがどーーーーーーしても上手くいかず、
基本から勉強しなおすために慌てて手に取った一冊。
ひとことでまとめると、
「要件とは『何を作るか』、設計とは『どう作るか』」っつー違いを理解して、紙を書こうね、というお話。(多分)
断片的に知っていたことを改めてまとめるには、良かったです。
ただ、あまりに内容が現場に寄り過ぎて、結局
「要件はなかなかまとまらないものだという前提の上で、作業を進めましょう」だの
「臨機応変に対応できないようにしましょう」だの
現実的過ぎる対処療法でオチがついてしまっているので、夢はないですorz
上流工程だけでなく、テスト仕様の話も出てるので、コーディング以下の下流工程の仕様で悩んでいる方も、どうぞ。
AMAZONの商品ページはこちら。
2009年8月読了。
最近の仕事で、
「要件定義 ⇒ 設計(仕様)」 のところがどーーーーーーしても上手くいかず、
基本から勉強しなおすために慌てて手に取った一冊。
ひとことでまとめると、
「要件とは『何を作るか』、設計とは『どう作るか』」っつー違いを理解して、紙を書こうね、というお話。(多分)
断片的に知っていたことを改めてまとめるには、良かったです。
ただ、あまりに内容が現場に寄り過ぎて、結局
「要件はなかなかまとまらないものだという前提の上で、作業を進めましょう」だの
「臨機応変に対応できないようにしましょう」だの
現実的過ぎる対処療法でオチがついてしまっているので、夢はないですorz
上流工程だけでなく、テスト仕様の話も出てるので、コーディング以下の下流工程の仕様で悩んでいる方も、どうぞ。
技術書というより、単なる読み物ですが…
『ウェブ進化論 本当の大変化はこれから始まる』梅田望夫(ちくま新書)
『ウェブはバカと暇人のもの』中川淳一郎 (光文社新書)
AMAZONの商品ページはこちらとこちら。

セットで軽く読んでおくと
「ネット活用の理想と現実」が見えて楽しいでしょう。
さくっと読めます。
『ウェブ進化論』のほうは、ネットが広がり、根付いてゆくことにより、社会の仕組みのどんなところが変わっていくのか、論じている。
2006年刊行の本だけど、たぶん、まだまだ内容は古くなっていない。
(…それはウェブの進化が実は遅い、という傍証なのですかねー)
私が読み取れたのは:
ネットの発達によって、これまでは(メディアの大企業など)「権威」あるものの特権だった「(ニーズや表現を)発信する手段」を、一般人も手に入れた。
↓
・「恐竜の尻尾」(≒ニッチなニーズ)を幅広く汲み上げる仕組みを作るという新しいビジネススタイルが生まれる
(AMAZONの、マイナーな本を、限りなく無限に提供できる仕組み、など)
・玉石混合の個人のネットコンテンツも、何万、何十万という人々が表現することにより、一定の割合で存在する「玉」の数も、絶対的に増えてきている
・玉石混合のネットコンテンツ「石」の部分をどうより分けるか、その検索技術の高まりも、ネットの価値を高めている
…とかなんとか。
あと、昨今のキーワードであるクラウドの話も、「ネットの『あちら側』に情報発電所を構築する」という表現で、主にグーグルを例に述べています。
クラウドの何がすごい?と心の片隅で思っている私も、この概念の成立経緯が見えたような気がして、少し理解が深まりました。
(ものごとや概念の由来を理解するって、大切だわね)
『ウェブはバカと暇人のもの』は、そんなすごい可能性を秘めているウェブというツールも、そもそもユーザに「凡人」「それ以下の人(バカ)」が増えすぎてしまったために、「玉」より「石」ばかり増殖しているという筆者の実感を、生々しくつづった一冊。
「ヘビーネットユーザは『暇つぶし』にネットを使うが、リアルに儲けている人たちは『情報収集』のためにネットを使い、さらに儲ける」
…というくだりは、自分の実感としても、すごく納得がいくんだよねw
(ブログに読書感想文書く暇があったら、もう一冊技術書でも読むか、10kmくらい走って来い、とw)
「ネットの影響力は、しょせんTVにはかなわない」「企業はネットに期待しすぎである(=Web2.0といいつつ、使いこなせていない)」という記述にも同意。
ゲームしたりマンガ読んだりするのと同じような「趣味」のネット利用の楽しさはよく分かっているし否定もしませんが…
個人のネット利用者は、「ネットの世界での人生の充実」は「リアルな世界での人生の充実」の補助要因でしかないということを忘れると、結局おいてきぼりにされますよー。ということでよろしいでしょうか、著者の方。
『ウェブ進化論 本当の大変化はこれから始まる』梅田望夫(ちくま新書)
『ウェブはバカと暇人のもの』中川淳一郎 (光文社新書)
AMAZONの商品ページはこちらとこちら。
セットで軽く読んでおくと
「ネット活用の理想と現実」が見えて楽しいでしょう。
さくっと読めます。
『ウェブ進化論』のほうは、ネットが広がり、根付いてゆくことにより、社会の仕組みのどんなところが変わっていくのか、論じている。
2006年刊行の本だけど、たぶん、まだまだ内容は古くなっていない。
(…それはウェブの進化が実は遅い、という傍証なのですかねー)
私が読み取れたのは:
ネットの発達によって、これまでは(メディアの大企業など)「権威」あるものの特権だった「(ニーズや表現を)発信する手段」を、一般人も手に入れた。
↓
・「恐竜の尻尾」(≒ニッチなニーズ)を幅広く汲み上げる仕組みを作るという新しいビジネススタイルが生まれる
(AMAZONの、マイナーな本を、限りなく無限に提供できる仕組み、など)
・玉石混合の個人のネットコンテンツも、何万、何十万という人々が表現することにより、一定の割合で存在する「玉」の数も、絶対的に増えてきている
・玉石混合のネットコンテンツ「石」の部分をどうより分けるか、その検索技術の高まりも、ネットの価値を高めている
…とかなんとか。
あと、昨今のキーワードであるクラウドの話も、「ネットの『あちら側』に情報発電所を構築する」という表現で、主にグーグルを例に述べています。
クラウドの何がすごい?と心の片隅で思っている私も、この概念の成立経緯が見えたような気がして、少し理解が深まりました。
(ものごとや概念の由来を理解するって、大切だわね)
『ウェブはバカと暇人のもの』は、そんなすごい可能性を秘めているウェブというツールも、そもそもユーザに「凡人」「それ以下の人(バカ)」が増えすぎてしまったために、「玉」より「石」ばかり増殖しているという筆者の実感を、生々しくつづった一冊。
「ヘビーネットユーザは『暇つぶし』にネットを使うが、リアルに儲けている人たちは『情報収集』のためにネットを使い、さらに儲ける」
…というくだりは、自分の実感としても、すごく納得がいくんだよねw
(ブログに読書感想文書く暇があったら、もう一冊技術書でも読むか、10kmくらい走って来い、とw)
「ネットの影響力は、しょせんTVにはかなわない」「企業はネットに期待しすぎである(=Web2.0といいつつ、使いこなせていない)」という記述にも同意。
ゲームしたりマンガ読んだりするのと同じような「趣味」のネット利用の楽しさはよく分かっているし否定もしませんが…
個人のネット利用者は、「ネットの世界での人生の充実」は「リアルな世界での人生の充実」の補助要因でしかないということを忘れると、結局おいてきぼりにされますよー。ということでよろしいでしょうか、著者の方。
カレンダー
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
最新記事
(01/04)
(06/19)
(01/03)
(08/04)
(06/29)
(05/26)
(04/28)
(03/10)
(02/03)
(01/05)
(11/23)
(08/16)
(07/29)
(07/05)
(05/01)
(02/20)
(12/31)
(08/20)
(08/19)
(08/18)
(08/17)
(08/16)
(08/15)
(08/14)
(08/06)
カテゴリー
プロフィール
HN:
兄貴ファン or まるこ
性別:
女性
職業:
なんちゃってSE。社畜です…
趣味:
まったり週末ランニング
自己紹介:
学生時代にお勉強させられた英語とかドイツ語とかを活用して、欧州サッカーとかジャパニメーションとか海外オークションとかで、貴重な余暇を非生産的につぶします。
時折走り、まれに勉強します。
2015年夏、乳がん(ステージ1)発症しました。
時折走り、まれに勉強します。
2015年夏、乳がん(ステージ1)発症しました。
ブログ内検索
アーカイブ
カウンター
